|
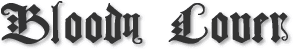
7
そして再び、時はさかのぼり深夜。アルテュールの帰ったアルダーソン邸にて―――。
ロースト子爵ジェルヴェは、長い間自室の鏡の前で凍りついたように、半分腰が抜けたような状態で立ち尽くしていた。口は叫びを張り付かせたまま。胸をはだけさせたまま。
夜も更け、静かな室内に響くのは、ジェルヴェの小さな呼吸音のみ。
どれくらいだろうか。
あのアルテュールが忽然と姿を消してから、ゆうに半刻たった後、軋むような動作でジェルヴェは立っていた姿勢の悪さに力尽き、わずかによろめいた。
それがきっかけとなり、ざわざわとジェルヴェの中がうごめきだす。
勢いよく、数十分という過ぎ去った時間をとりもどすかのように脳が活動を始める。
目は冴え冴えと光を取り戻し、あたりをゆっくりと見回す。
ふっとジェルヴェは上を見、下を見、そして左右に首を振り、おもむろに右手をあげると自ら頬を打った。
遠慮なく自分自身に向かって繰り出された拳。
「……ぅぐッ!」
そうしてようやく正気に戻ったジェルヴェは、頬の痛みに冷や汗をたらし呟いた。
「……あれは夢では……ない」
そう。
あの、目の前でアルテュールが霧のように消えたこと。
どう考えようと見間違いではなかった。
そして、自分の胸に、まるで悪しき呪いのように浮かんでいる蜘蛛の巣のような赤黒い文様も。
指先でそっと触れてみると、呼応するようにドクリとざわめく。
不快さにジェルヴェは眉を寄せた。
アルテュールがこれをしたのだろうか?
いや違う、あの男はこれを見て驚いていた。
ジェルヴェは考えながら、あごに手をあて、そしてアルテュールの来訪した目的を思い出した。
『妹に近づくな』
そうアルテュールは言った。
妹。アデール・ローペルヌ。
ジェルヴェの首に噛み付いた、あの美少女。
「…………ま、まさか」
噛み付かれた瞬間、なにか鋭いものが皮膚を突き破って侵入してきたのを覚えている。
あれは――――牙、だったのだろうか。
そこまで思い至った次の瞬間、ジェルヴェは突風のごとく部屋を走り出た。
ドタバタと静かな廊下を大きな足音を立てて走る。
田舎のこの屋敷にいるわずか数名の使用人たちもすでに寝入っている時間だ。
ジェルヴェは昔一度だけ入ったことのある部屋目指して突き進んだ。そして大きな音を響かせて扉を開く。
とたんに鼻腔をくすぐるのは部屋中に敷き詰められた書物の匂い。
そこは書斎だった。
ジェルヴェは駆け込むと、書棚にぎっしりと敷き詰められた背表紙を必死に目を走らせる。
いくつかを乱暴に取り出してはページをめくり舌打ちする。それを数回くりかえした後、ようやくジェルヴェの手に一冊の本が残った。
とあるページを開いたまま、大事そうに抱え、書斎を勢いよくあとにした。
息せき切ってジェルヴェが次に向かった先は台所だ。普段まったくジェルヴェが入ることなどない台所を盗人のように荒らす。
「くっそ! どこにあるんだ!!」
歯軋りしながら大きな物音をたてて書斎と同じように荒らす。しばらく探してようやく目当てのものを見つけたジェルヴェはそれが入った籠ごと本とともに抱えた。
「―――お、おぼっちゃま!? なにをなさっていらっしゃるんです」
と、台所の入り口に灯りがひとつたった。ランプを手にしたのは古くからこの屋敷に働く40代の侍女セレナだ。最近ちらほら目立ってきた白髪を気にかけているセレナはネグリジェにショールを羽織り、目を見開いている。
ジェルヴェはキッと視線を向けると、大またで歩みよった。
「おい! セレナ! いまから言うものを至急俺の部屋まで運ぶんだ!」
「は、はぁ?」
「いいか! まず家にあるあらゆる十字架を集めろ! それと銀だ! あとは――――」
大きな声でまくしたてるジェルヴェにセレナはこれ以上ないほど呆けている。そしてジェルヴェの言葉に義務的に頷きながらも、その視線はジェルヴェの抱えた本と籠に向けられた。
籠に山盛りに入っているのは、大量のニンニク。
いったい何に使うのだろう、そんなことを思うセレナに指示を出すと、ジェルヴェは籠を大事そうに抱えて自室へと戻っていったのだった。
そうしてジェルヴェが指示を出したものがすべて揃った―――、一刻後。
セレナをはじめとした屋敷の使用人たちは一様に呆然としていた。セレナはぽかんと大口を開けてしまいそうになるのを必死で我慢している。
都の本宅ではないにしろ、ここは公爵家の別邸なのだ。その使用人がしまりのない顔をできるはずがない。
そう思いつつも、どうしようもなくセリナたちは呆けた顔をしてしまっていた。
そしてセレナにそんな顔をさせているのは、なにやらぶつぶつ唱えている青年だった。
都で轟かせた伊達男の名の片鱗などまったくない、奇妙な格好をした青年。
言わずもがな、ジェルヴェ。
頭にはニンニクで作った冠をし、首にもニンニクと、そしてロザリオを3個ほど。部屋のいたるところにニンニクが並べられ、たくさんの蝋燭が煌々と火をともしている。数枚の姿見や、小さな鏡も四方に並べられている。
異様な、光景だった。
ジェルヴェのために新たにしつらえた部屋の調度品たちは最高級のものだというのに、いまは妖しい蝋燭の灯に照らされなんともいない佇まいをかもしだしていた。
「あ……あのおぼっちゃま……」
十字架を手に、聖書を読みながらブツブツ呟いているジェルヴェに、ようやくの思いで声をかけたのはセレナの横にいた執事ランドだった。
もうじき60に手のかかるランドは皺の多い顔の眉間にさらに皺をつくり、細い目でジェルヴェを見つめている。
「なんだ」
ギッと鋭く視線を返すジェルヴェ。
ランドはわずかに困惑をにじませながらも、「これはどういったことでしょうか」と冷静に尋ねた。
「どういったことだと!?」
ジェルヴェは声を荒げ、あの領主の兄妹のことを言いかけた。
だが寸でのところで喉を詰まらせ黙り込む。
『ローペルヌの兄妹は吸血鬼だ! だからその対策だ!』
そう言いたかった。
実際吸血鬼だとするのならば、皆に告げるべきなのだろう。
そしてローペルヌ家を打つべきなのかもしれない。
が、しかし何故かこのときジェルヴェは自分自身を見下ろし、ニンニクの強烈な香りにほんの少し冷静さを取り戻した。
都では華やかな毎日を送り、女からは熱いまなざしを向けられ、男からは嫉妬を向けられていた。
幾多いる貴族の中でも家柄を始め顔や頭に揺ぎ無い自信をもつジェルヴェ。
それが―――いまの状況はなんのだろうか。
頭にはニンニク、手に聖書と十字架。
すべてあの―――吸血鬼兄妹に対するもの。
まるで、恐れている、という証そのもの。
それに気づき、ジェルヴェは歯軋りをすると使用人たちから顔を背けた。
「お前らには関係のないことだ! とっとと寝ろ! ……それといいか! 俺を訪ねてくる者がいても、ぜったいに屋敷に上げるな!!」
そう叫ぶと、ジェルヴェは皆を追い出したのだった。外にいる使用人たちがしばらくして散っていく足音を確認して、ジェルヴェはようやくため息をついた。
「この俺様が……吸血鬼を怖がっているなど認めるか!」
吐き捨てるように呟き、ジェルヴェは頭につけているニンニクの王冠に手をかけた。
力任せに引っ張り―――かけ、止める。
ニンニクに触れたまま逡巡する。数秒して忌々しげに舌打ちすると、開きっぱなしだったカーテンをすべて閉めていった。
そして柔らかい肌触りの毛布をベッドから引きずり下ろすと、頭からそれを被る。
顔だけだした状態で、ジェルヴェはふとした瞬間に歯軋りしては、十字架を握り締め、聖書に目を落としたのだった。
怖いわけではない!!、と心の中で呟きながら。
そうしてジェルヴェが眠りについたのは朝日が昇ったころだった。
吸血鬼は陽が昇る前に眠りにつく。
そう――ジェルヴェが足元に置いている『世界の怪奇辞典』に書いてあったのだ。
だから、朝日を見たとたんにジェルヴェは無意識のうちに緊張を解き、深い眠りの底に落ちていったのだった。
それから、約11時間後。
なぜそんなにも寝てしまっていたのか。ひどく楽しい夢をジェルヴェは見ていた。
沢山の女たちに囲まれ、尽くされるという、楽しい夢だ。
夢の中で四方から女たちにキスの嵐を受け、ジェルヴェは仕方がないなと、ふんぞり返っていた。
『ジェルヴェさまぁ』
甘ったるい声で女たちがしなだれかかって来る。
『ジェルヴェ様』
『まぁ待て。順番だ』
夢の中でジェルヴェは笑いながら言う。
『ジェルヴェ様』
『ああ、わかったから。待てと言っているだろう』
ねだるような女の声に、仕方なさそうにジェルヴェは女を引き寄せる。
『ジェ、ジェルヴェ様……』
恥ずかしそうに女が頬を染める。
『恥ずかしがる必要などない』
ジェルヴェはくつくつと笑いながら女を抱きしめると、上を向かせ口付けをした。
「ジェ……ルヴェ様」
うっとりしたような―――声。
そして、体温。
やけにリアルな夢だ。
そう、思った。
そしてその瞬間唐突に、ジェルヴェは目を開いた。
夢から現実へ―――。
目覚めたジェルヴェの目に飛び込んだのは、愛らしく美しい容姿をした少女。
「おはようございます、ジェルヴェ様」
頬をほのかに染め、ジェルヴェの腕の中にいたローペルヌの娘アデールが微笑んだのだった。
BACK TOP NEXT
2006,11,19
|