|
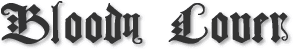
6
アルテュールがジェルヴェのもとを訪れる2時間ほど前。
アデールは自室でメイド・サリーへ今夜の運命の出会いを話していた。
「……お嬢様……、本当にジェルヴェという殿方が"儀式"をされたのですか?」
一通り聞いたあと、サリーは確認した。その手はアデールのプラチナブロンドの髪をゆるく三つ編みにしている。
鏡台の前に座ったアデールは白地に薄いピンクの花模様を刺繍したネグリジェを着ていた。
表情はいつにもまして楽しそうで、喜びに溢れている。
儀式のことがずっと頭の中にあるのだろう。その瞳はうるみ、うっとりとしていた。
「そう。ジェルヴェ様。サリーは知っている?」
まだ社交の場に二度しか出ていないアデールは、あまり詳しく出席していた者たちの名を知らない。
その点サリーは使用人ではあるが、外との交流も多く、知識も豊富なのだ。
「……はい。恐らく先日都からいらした伯爵のご子息でもあり、ロースト子爵でもある方かと思います」
「まぁ! ジェルヴェ様はそんなに素晴らしいかたなのね」
一つジェルヴェのことを知っただけで、アデールは嬉しそうにさらなる笑みを広げる。
サリーはそんなアデールを鏡越しに見ながら、そっと胸のうちでため息をついた。
若くして地位も名誉ももっているジェルヴェがなぜこんな田舎に来たのか、それはこの狭い町にあっという間に広まっている。
女癖の悪さは右にでるものがいないほどだったという。
たとえ身分が上の貴族令嬢であれ、貴族夫人であれ、気に入れば手をつける。
そして一夜限りであっても、女はたちまち彼に溺れたとか。
それがどこまで真実であるかはわからないが、女に手が早いということは確かだ。
「ジェルヴェ様はまだお若くていらっしゃいますが、お父上である伯爵様について事業にも参加され、とても有能な方と認められていたと聞いております」
おそらく今日アデールに近づいたのも、戯れ程度の気持ちだったことには間違いないだろう。
だが、それがなぜよりにもよって"儀式"の形式をとってしまったのか。
運命の悪戯―――、としか言いようがないだろう。
かろうじて、まだ途中だったというから、きっと"儀式"が完了することはないと思うが。
アデールが続きを望んでも、彼女の兄アルテュールがそれを許すはずないのは確実だ。
こうしてアデールがゆっくりしている間にも、妹を溺愛している兄はジェルヴェを牽制するために動き出すことだろう。
ジェルヴェについて聞きかじっていたことを話していたが、いつの間にか手は止まり、サリーは思わずため息をこぼしていた。
「どうしたの? サリー?」
アデールが小首を傾げて、愛らしい顔で見上げてくる。
慌てて笑みを作って、サリーは首を振った。
「いいえ、なんでもございません。………お嬢様、今日はもうお休みになられますか? それとも明日のお召し物をお選びいたしますか?」
明日になると、この少女は初めての恋を失った哀しみに涙にくれるのだろうか。
そんなことを思いながら、サリーは優しい眼差しを向けた。
アデールはパッと顔を輝かせて、頷く。
「ええ! 一緒に選んでくれる、サリー?」
満面の笑みで聞いてくるアデールに、もちろんです、とサリーは笑みを返す。手早く編みあがったアデールの髪をシルクのリボンで結ぶ。
「お嬢様にもっともお似合いになる、可愛らしいものを選びましょうね」
そう言うと、アデールはさらに笑みを大きくして椅子から立ち上がった。
衣裳部屋へと軽い足取りで向かうアデールの後姿を眺め、サリーはちらり窓の外を見やった。
窓には外の深い闇と、室内の明るい様子が鏡のように映し出されている。
"儀式"は途中で中断されていた。
あのロースト子爵ジェルヴェは、本人にとっては幸いなことだっただろう。
しかしアデールにとっては―――。
「サリー? 早く早く!」
アデールの鈴の音のような玲瓏な声が響く。
サリーは、すぐ参ります、と言いながら衣裳部屋へと向かった。
(失恋されるお嬢様のためにあらゆるお菓子を用意しておかねば)
まだ幼いアデールのためにと、サリーは明日準備すべきことを考え出したのだった。
だがアデールも、サリーもまだ知らなかった。
すでに"儀式"は終了間際だったことに。
***
吸血族の長であるローペルヌ一族。
その末娘アデールは、ゆるやかな眠りから目覚めた。
眠りから現への目覚めをうながしたのは、すがすがしいローズマリーの香り。
サリーが毎日目覚める時間に合わせて精油を焚いてくれているのだ。
いつもは日が暮れてから目覚めるが、今日は早めに起きた。窓の外には傾いた太陽が、滲むようなオレンジ色の光で世界を照らしている。
アデールは起き上がると、大きく伸びをし、ベッドから降りた。
普段より起きる時間が早いためか、まだ少し眠い。
巷で広まっている吸血族についての噂は太陽を浴びると灰になるとかいうものらしいが、アデールたちには当てはまらない。
それだけでなく、ほかもいろいろと、だ。
噂の根源となっているのはアデールたち吸血族とは、また違う者たちだ。
アデールは分厚いカーテンを少しだけ開け、あまり馴染みのない太陽を眺めた。
"あちら"の世界はいつも夜のため、めったに昼間というものを見たことがないが、光にいろどられた世界は輝くように綺麗でアデールは好きだった。
「お嬢様」
声をかけられ振り向くと、サリーがやってきた。
「サリー、おはよう」
にっこりと笑顔を浮かべ、ソファに腰を下ろした。
テーブルの上に、サリーがお茶の用意をする。
これも毎日のことで、起きてすぐにハーブティーを飲むのが習慣だった。
ガウンを羽織っただけのネグリジェ姿のアデールはビロード地のソファに腰を下ろし、ハーブティーを口元に運ぶ。
爽やかな香りが口の中に広がる。
しばし起きぬけのティータイムを楽しんだ後、ネグリジェから明け方まで選びに選んだドレスを着、そしていつも以上に時間をかけて髪のセットとお化粧をサリーに施してもらった。
白銀の髪を両耳の横で一房づつ薄いピンクのリボンとともに編みこみ、緩く波打った髪は背にゆったりと広げたまま。
愛らしい小さな純白のレースのリボンをふんだんにあしらった薄いピンクのドレスはアデールをこれ以上ないほど清楚に彩っていた。
逸る気持ちに一時も早くジェルヴェの元へ行きたいとアデールは胸元を押さえソワソワする。
「お嬢様、今日は一段とお美しゅうございます」
ドレスのすそを綺麗に広げていたサリーがアデールの全身を眺め満足げに言った。
アデールははにかんで頬を朱に染める。
「お食事はよろしいのですか?」
「ええ。………ああ、でも少し一杯だけ飲んでおこうかしら」
「それでは用意してまいります。しばらくお待ちくださいませ」
サリーが頭をたれ、部屋を辞す。
一人残ったアデールは大きな姿見の前に立つ。
一点でも乱れがないか気になって、じっと鏡の中の自分を見つめる。
鏡の中の自分は少し緊張しているように見えた。
そっと手を伸ばし鏡の表面に触れる。と、鏡は波打ったように小さく揺れる。
こちらの世界の者ではないアデール、そして"あちら"の住人は鏡に姿を映すことはほとんどできない。
例外もあり、訓練をつめば鏡に映ることもできるようになる、が、まだアデールには不得意な分野だった。
いまアデールを映している鏡は、特殊な魔力を用いてつくられた"あちら"の住人を映すことのできるものなのだ。
「ジェルヴェ様、気に入ってくださるかしら」
鏡を見つめ、だが遠くジェルヴェの姿を思い出したながら胸を締め付ける甘い苦しさに、ため息とともに呟く。
と、後ろ髪がわずかに揺れる。
「こんなに美しいアデールを気に入らない者などいるというのかい?」
鏡には何も映っていない。
だが耳朶を打つ凛とした声に、驚くことなくアデールは微笑み振り返る。
アデールの髪を一掴みし、そこへ口づけを落としているのはアルテュール。
「アルお兄様」
頬を緩めたアデールの頬に手を滑らせ、やさしい微笑をアルテュールは向ける。
「おはよう、アデール」
そっとアルテュールは挨拶のキスをアデールの額に落とした。
「今朝はよく眠れたかい?」
「ええ。夜はとってもドキドキしていたけれど、ぐっすり眠れましたわ」
にっこりとアルテュールを見上げるアデール。
「そう。それはよかった。―――アデール」
アルテュールが静かに声をかけた時、ちょうどノックの音が響きサリーが戻ってきた。そして一緒に入ってきた一人の幼い少女。
「おはようございます」
軽やかな声で挨拶をする少女の名はエリス。齢13の、れっきとした人間の娘だ。そしてアデール付の侍女である。
侍女といっても世話をするわけではなく―――その役割はアデールの"食事"だ。
エリスは愛らしい瞳でアデールを見上げると、白く細い首筋を見せた。
いつものように、アデールはエリスの肩にそっと手を置き、その首筋に唇を近づける。
エリスの体がから立ち上る馴染みある芳香。なにも香水などつけていないが、処女の血は吸血族にとって得もいえぬ香りを漂わせているのだ。
やにわに、アデールの唇の両端から牙が出、エリスの首筋に突き刺さった。
いつものように、血を吸う。
エリスは苦しがるでもなく、逆にうっとりとした表情で身をまかせている。
だが、数秒とおかずにアデールは身を離した。
いつもなら軽い貧血程度にエリスがなるくらいまでは、血を飲む。
だが今日はほんの少しだけだ。
アデールは口元を押さえて眉を寄せた。
唐突に食事を終えられたエリスは戸惑いがちにアデールを見つめる。そしてサリーもまた。
「いかがなさいました? お嬢様」
サリーが訝しげに聞くと、アデールは目をしばたたかせて口を開きかけた。
だが、言いよどむ。
アデールにとって、初めてのことだった。
昨日までとてもおいしかったエリスの血が、今日はとても苦く、吐き気を感じたなど。
それを素直に告げるのは、不安そうに見上げているエリスに気の毒で、アデールはしばし逡巡した。
「……エリス、今日は体調が悪かったりする?」
アデールの問いに、エリスは一瞬きょとんとした。が、すぐに困惑したように目を潤ませる。
「いえ……なにも。お嬢様、私の血お口に召しませんでしたか?」
アデールは視線を泳がせて、あわてて首を振った。
「そんなわけないわ! あ、あの…私、寝不足みたいなの。それであまり食欲がないみたいだわ。ごめんなさいね、エリス」
エリスの手をとって、必死に言いつくろう。それでも不安げなエリスに、笑顔で大丈夫よというように見つめた。
しばししてようやくエリスは小さく頷いたのだった。それからエリスが部屋を辞して、アデールはため息をついた。
「お嬢様、エリスの血に問題が?」
様子を見守っていたサリーが問いかける。
アデールははっとして、心配そうなサリーと、そしてアルテュールを交互に見つめた。
「あのね……。なぜだかわからないんだけど……すごく苦くって……飲めなかったの」
サリーは「えっ」と声を上げる。だがアルテュールはなんの反応も示さない。
「私……どこかおかしいのかしら?」
両頬を包むように手をあてて、アデールは呟いた。
「………お嬢様、まさか――――あのジェ……」
サリーがなにか言いかけた。アデールが視線を向けるも、言葉は途切れたまま。
すぐにサリーが「なんでもありません」と首を振る。
「たまたまアデールとエリスの調子が合わなかっただけだろう。そういうこともあるのだよ」
緊張を解くような優しいアルテュールの声が響く。
穏やかな兄の微笑みに、アデールは「そうですわよね」とほっとしたように頬を緩めた。
だが、サリーだけは、複雑そうな表情でアデールを見ている。
サリーの中に湧き上がった疑問を告げることを中断させたのが、兄アルチュールの冷やかな眼差しだったことを、アデールが知る由もなかった。
BACK TOP NEXT
2006,10,19
|