|
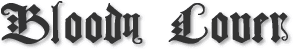
誓いのくちづけ 2
アデールは重くため息をついた。
先日16歳の誕生日を迎えたのを機に、社交界デビューしたばかり。
それまではとくに社交の場へ赴くことも、これといった友人もいなかったのだ。
両親と兄弟たちから蝶よ花よと育てられた結果、アデールにとって家の敷地を一歩踏み出せばそこは別世界のようにさえ感じられた。
田舎町であるドルドンは人口も少ない。領主であるアデールの父をはじめ、貴族や地主などで小さな社交界が築かれている。
まだまだ慣れない社交の場の華やか過ぎる空気にあてられ、アデールは疲れきっていた。
兄アルテュールを見ると、兄はご婦人や殿方に囲まれ談笑している。
日頃無口なアルテュールだが夜会にでれば人気者で、洗練された社交術で人々の中心となっている。
アデールもまた美しさゆえに皆から話し掛けられることも多いのだが、なかなか会話を続けることができないでいた。
ぼんやりと兄を見ていると、ちらり心配げにアルテュールが視線をよこす。
迷惑をかけてはいけないと思い、アデールはにっこりと笑顔を浮かべた。
なんとか馴染まねばとアデールは一人ふらふらと広間を歩き出した。
しばらくして主催者である男性が合図をし、ダンスが始まった。
「大丈夫かい、アデール」
アルテュールがやってきて、心配そうに覗き込む。
兄の手をとりながらアデールは笑顔で頷く。
「心配なさらないで? 見てるだけでも楽しいし、それに少しづつでも色んな人と喋れるようになりたいと思っているから。だから私のことは気にしないでね」
言葉を捜しながら伝えると、それでもアルテュールは心配そうにしている。
「踊りましょう?」
「……ああ」
アルテュールはようやく微笑し、アデールをリードしダンスをはじめた。
ゆったりとしたリズムの曲がしばらくして終わると、今度はリズミカルなものにかわる。
兄から老齢な男性へとダンスの相手が代わる。
相変わらずアルテュールは心配そうにしていただが、明るい笑みを見せ、父親くらいの歳の男性とダンスを楽しんだ。
それから一人、二人とダンスの相手が代わっていった。
踊り疲れダンスの輪から抜けようと思ったとき、手がつかまれた。
申し訳ないが断ろう――――、そう手をつかんだ男性を見上げ、アデールは息を止めた。
深い藍色の瞳が、アデールを射抜くように見下ろしていた。
整った顔立ちの精悍な青年だった。兄アルテュールとは違う美しさを持った青年。
なぜか目をそらせずに、アデールは青年を見つめる。
「――――大丈夫か?」
青年が言った。
まるで知り合いであったかのように声をかけられ、アデールは目をしばたたかせる。
「顔色が悪い。少し風にあたったほうがいいと思うぞ?」
青年の手がそっとアデールの頬を撫でた。
頬をすべる指の感触に、アデールは我にかえる。急激に頬が熱くなるのを感じた。
家族や使用人以外のものに触れられたことなどあるはずもない。
アデールは視線を泳がせて、うつむく。
「テラスから出たところにベンチがあったから、夜風にあたって少し休んでいるといい」
青年はそう言って、アデールにグラスを渡した。
薄い琥珀色をしたものが入っている。
「ここにいるとまた誘われるかもしれないぞ?」
ぽんと背中を押され、ようやくアデールはおずおずと口を開いた。
「あ……の、ありがとうございます」
青年は微かに口元を緩めた。
アデールは再び青年に見惚れかけ、慌てて視線をそらすと会釈してテラスへと向かった。
青年の言うとおりベンチがあり、アデールは腰を下ろした。そして青年からもらったグラスに口をつける。
ほのかに苦味のある味。シャンパンだった。
お酒を口にしたことはほとんどなかったが、なんとなく一口二口と舐めるようにちょっとだけ飲んでみた。
傍らにグラスを置き、ほっと息をつく。
夜風は涼しく、気分は少し落ち着いた。
それと同時にさきほどの青年のことが気になった。
初めてあったはずだ。それなのに心配し気遣ってくれたということが驚きで、そして妙に嬉しかった。
「もっときちんとお礼を言っておけばよかったわ」
ぽつり呟いて、アデールはベンチにゆったりともたれかかった。
と、カチンと音がした。手にひんやりとした感触がして、驚いて見るとグラスを倒してしまっていた。
アデールは慌てて立ち上がる。ドレスが濡れることはなかったが、手袋が濡れてしまった。
ため息をついて、アデールは手袋をはずした。
そして、そのとき、指輪が落ちた。
指輪は石畳の上をころころと転がる。
母親から譲り受けた大切な指輪。
指輪は音もなく、しずかに幾度か回転して止まった。
ほっとして、アデールは指輪をとろうとし、気づいた。
指輪のそばに立ち止まった足に。
つと視線を上げる。
ちょうど屈み、指輪を取る姿が目に映った。
指輪をとったのは、さきほどの青年。
「あ………」
まっすぐに青年の視線が注がれる。
その視線に絡めとられてしまったように、アデールは動くことができなかった。
そして――――、言葉にはできない、なにか予感めいたものを感じていた。
***
アデールという少女は典型的な箱入り娘のようだ。
ほんの少し頬に触れただけで真っ赤になっていた。
あれなら落とすことなど容易いだろう、そうジェルヴェはテラスへと消えていったアデールを思い出し唇を歪める。
ちらり視線を流し、アデールの兄であるアルテュールの動向を伺う。主催者の妻である女性とダンスをしていた。
邪魔者もいないことだし、さっさと追いかけるか。
ジェルヴェは気配を消すようにして広間から抜け出した。
テラスへでるとアデールが立ち上がって地面を見ている。
怪訝に思い、その視線をたどると、ちょうど自分の足元にアデールのものと思われる指輪が転がってくるところだった。
ジェルヴェは指輪を拾い上げる。
小指の先ほどのダイヤをあしらった指輪だった。
アデールを見ると、固まったように立ち尽くしている。
『ジェルヴェに見つめられると動けなくなってしまうの』
この田舎へくる原因となったさる貴婦人がしなだれかかって、そう言っていたのを思い出す。
女は意外と見つめられると弱いものだ―――、とジェルヴェはアデールに視線を止めたまま思う。
ジェルヴェは一歩、一歩ゆっくりとアデールに近づいていった。
アデールは身じろぎひとつせずジェルヴェを見つめている。
(さて―――どうするか)
アデールの目前まで来て、ジェルヴェは一瞬考えるも、すぐに小さな笑みを口元にのぼらせた。
きっとお姫様のように可愛がられ育てられたのだろう。
だとすれば、そのように扱えばいい。
ジェルヴェはすっとアデールの前に片膝をついた。
アデールは驚いたように目を見開いている。
笑みを消し、真剣さを装い、ジェルヴェは改めてアデールを見つめると、その手を取った。
そして、指先に、口付けを落とした。
ほんの戯れ。
だがまさかそれが―――自分の運命を大きく動かすことになるとも、知らずに。
BACK TOP NEXT
2006,9,21
|