|
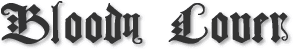
誓いのくちづけ 1
手を取り、その指先に口付けを落とす。
薬指に指輪をはめ、再び今度は指輪に口付けを。
そして誓いの言葉を告げる。
最後に――――誓いの口付けを交わし、
二人は永劫、ともに在る、のだ。
それは、古より伝わる、"誓いの儀式"だった。
***
「アデール」
艶やかで人の心を惹く声が、響いた。
螺旋階段の下、手すりに手をかけ佇む声の主は20代前半くらいの様相をした美しい青年だった。
「アルお兄様、お待たせしてごめんなさい」
そう、はにかんだ笑みを浮かべ、アデールはメイドに促され螺旋階段を降りていく。
アデールと呼ばれた少女もまた美しさと愛らしさとを兼ね備えた少女だった。
プラチナブロンドの髪は綺麗に巻かれている。耳の後ろで、色とりどりの宝石を散りばめた髪細工が華やかに髪をまとめていた。
透き通るような真珠のごとき白い肌。ふっくらとした唇は深紅の薔薇のように麗しく、頬もまたほんのりと紅色に染まっている。
空の青さを封じ込めたような輝く瞳を、アデールは兄アルテュールに止めた。
メイドからアルテュールへとアデールの手がゆだねられる。
「今日のドレス、少し派手ではないかしら?」
アデールはアルテュールの腕に腕を絡めながら、緊張した様子で言った。
「そんなことはないよ。深い色合いの赤はお前をとても大人びて見せているよ。このやわらかく幾重にも重なったドレーブは可愛らしさを感じさせるし、胸元で光るサファイヤは白く美しい肌を際立たせている」
歯の浮くようなセリフを、軽がるしくない至極真剣な口調で言いアルテュールはアデールを見つめる。
「お前に似合わないものなどないよ」
そうアルテュールが微笑すると、アデールはほっとしたように頬を緩めた。
「ありがとう、アルお兄様」
社交界デビューしたばかりのアデール。今日はまだ2回目の夜会への参加だ。
緊張しきっている妹を優しくエスコートするアルテュールはふと、アデールの手に目を留めた。
シルクの長い手袋をつけた手、左の薬指に小さな石を冠した指輪が光っている。
「また、つけて行くのかい?」
「え? ええ……。あのお守りとして」
アデールははにかむように指輪に視線を落とす。それは母親から受け継いだものだった。
「………そう」
アルテュールは静かに笑み、そっとアデールを促した。
――――行ってらっしゃいませ。
そうして二人は、メイドに見送られ夜会へと向かったのだった。
「おや、久しぶりじゃないかい? ロースト子爵ジェルヴェ殿」
若い男の声が、口調は丁寧に、だがからかいを多分に含んで響いた。
ソファーにゆったりと足を組み座っていたジェルヴェは海の底のような深い藍色の瞳を冷たく男に向ける。
「久しく見ないうちに貧弱になったんじゃないか、エドモン」
彫りの深い精悍な顔をしたジェルヴェ。鍛えぬかれた体格は最上級の衣服の上からもわかる。
一目を惹く容姿ながら、態度は素っ気なく、ジェルヴェは向の椅子に腰掛けたエドモンに冷やかに言葉を発した。
「貧弱とは、相変わらず失礼な男だな、ジェルヴェ」
言いながらも、エドモンは楽しそうだ。
「見たままを言ったまでだ。田舎暮らしで、もうもうろくしはじめてるんじゃないか?」
ニヤリ、と口の端を持ち上げるジェルヴェ。
同じくエドモンもまた冷笑を浮かべる。
「まぁのんびりと過ごしてるさ。―――というか、そんな田舎へようこそ子爵殿」
笑いを含んだ歓迎の言葉に、ジェルヴェは大きなため息をつき、仏頂面でワインをあおった。
それを見て、ついに耐え切れないとばかりに口元に拳を当てて笑い出すエドモン。
「いやいや、まさかこんな田舎の夜会でお前と再会できるとは思わなかったぞ?」
一気に親しみ深くエドモンは目を細める。
二人の年齢は20。知り合ったのはまだ6歳という幼少の時だった。
エドモンの一家が数年前に没落するまでは都でいつもつるんでいたものだ。
ジェルヴェは答えることなく、自棄酒のようにワインを飲んでいる。
「噂は聞いたぞ。羽目を外しすぎ、親父殿をついに怒らせたそうじゃないか」
ジェルヴェの父親は伯爵位を持ち、都でもそれなりの権力を持っている。
ほんの一週間前、その父親からジェルヴェは勘当とまではいかなかったが、この田舎ドルドンの別荘に一時謹慎するように言われたのだ。
エドモンは楽しくてしかたがないといった様子で、ジェルヴェへと身を乗り出す。
「某公爵夫人に手を出した―――――、というのは本当か?」
田舎と言えど、おおっぴらに話せる内容ではない。エドモンは声を潜めて聞いた。
ジェルヴェはワイングラスを片手に、目を眇めエドモンを見つめる。
数秒の間のあと、
「俺が獲物を逃すとでも?」
再び笑みを刻んだ。
エドモンは小さく口笛を鳴らす。
「さすが、ジェルヴェ殿。確かあの公爵夫人は30歳になったばかりだったかな。味はいかほどだ?」
「まぁ、それなりにだな。一番美味いのはやはり―――若い」
と、ジェルヴェの言葉をかき消すように、ざわめきが室内に広がった。
都で行われる夜会ほど盛大でもないが、それなりに華やかな雰囲気だった広間。そこにいる招待客たちが、現れた一組の男女を見てため息をついていた。
見惚れずにはいられない美しい青年と、美しい少女だった。
仲睦まじく寄り添った二人。
少女は皆からの視線に恥かしそうにうつむいている。
ジェルヴェは遠目にその少女を見つめた。
エドモンに視線を向けもせず、尋ねる。
「あれは?」
「おや、もう目をつけたのか?」
「こんな田舎に期待していなかったが……。あれは」
美味そうじゃないか?、とジェルヴェの忍び笑いがこぼれる。
エドモンは苦笑しながら、「あの二人は領主一家ローペルヌの兄妹だ。兄のアルテュールとつい最近社交界デビューしたばかりのアデール」と教えた。
ワインを口にしながら、「アデールね……」とジェルヴェが呟く。
エドモンはちらりと兄妹のほうを見やり、そしてジェルヴェに囁いた。
「領主一家の大事な娘だ。あればかりは手を出すなよ」
旧友の言葉に、視線を戻す。ジェルヴェは僅かに眉を寄せるも、冷やかに笑う。
「手を出すな? お前に忠告をもらうとはな。だが――――」
ジェルヴェは最後まで言わず目を細めた。
アデールの月のようにやわらかく美しく輝く白い肌を見つめる。
若く美しい純潔の少女を、俺が逃すわけはないだろう?
ジェルヴェは心の中で呟き、薄く笑ったのだった。
TOP NEXT
2006,9,21
|