|
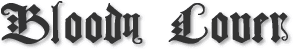
5
ふと目が覚めた。
暗い部屋の中。
ジェルヴェはぼんやりとした頭で身を起こし、見渡した。
そこは自室だった。
夜会に出かけたはずだったが、いつのまに帰ってきたのだろう。
いまいち記憶がはっきりしなかった。しかも、上着は脱いでいるものの夜会へ着ていった正装のままだ。
(……帰り際にエドモンと話したような気もするが、まぁいいか)
まだ窓の外は暗く静かだったが、ジェルヴェはベッドから降りた。
頭はぼんやりしているものの、眠気はない。
不思議な浮遊感を感じつつ、テーブルに置いてあった水を飲む。
ごくごくと飲んで一息つくと、少しだけ頭もはっきりしてきた。
と、はっきりしてくると不意に首筋に微かな違和感を感じた。
痛いわけではないが、なにかほのかな熱さがある。
ジェルヴェはランプに灯をともし、鏡の前にたった。
さして大きくない鏡を覗き込む。襟元を大きく広げ、首筋を見てみた。
「……………」
ジェルヴェは鏡に額が触れそうなほど顔を寄せて、目をこらす。
首筋に二つ傷があった。
小さな小さな二つの丸い穴のような傷跡。
それはまるで、なにかに刺されたようなものだ。
ジェルヴェはそっと手でその傷跡に触れてみた。
特に痛みはない。
だが触れた指先から確かな熱を感じる。
「なんだ………いったい」
そう呟いて、唐突に記憶が甦った。
「あっ!!! あの娘!」
そう、だ。なぜ忘れていたのか。
あのアデールという娘に噛まれたのだ。
そしてその時、急に頭に痛みを感じて――――。
「いったいなんだったんだ。あれ……は……」
ぶつぶつと言いながら鏡を背にし、ジェルヴェは目をしばたたかせた。
目前にソファーがある。
そこに、若い男が座っていた。
「………?」
ジェルヴェは呆けたように右を見て左を見る。
寝ぼけているのではないかと、己の頬をつねってもみた。
だがあきらかに自分は起きているし、それに自室に間違いない。
ということは?
ジェルヴェは再度ソファーを見る。
そこに若い男の姿はなかった。
「なんだ?」
「ロースト子爵ジェルヴェ・アルダーソン」
見間違いか、と訝しく呟いたジェルヴェの声に、見知らぬ声が重なって響いた。
目を見開き横を見ると、先ほどソファーにいた男がすぐそばに立っている。
驚くも、一歩後ずさり構える。
一応名門貴族の子息である。幼少の頃から武道のたしなみはあった。
「なんだ、貴様は!」
こんな深夜に、しかもまったくの気配もなく自分のそばにやってきた若い男。
寝ているうちに侍女が案内したとも思えない。
白銀の髪とサファイアのような瞳をした、美しい男だ。
身構えつつ、ジェルヴェはどこかで見たことがあると気づいた。
「………お前……確か領主の息子か?」
アデールとともに夜会に来ていた兄。たしかアルテュールと言っていた気がする。
訝しげなジェルヴェの視界の中で、アルテュールはゆっくりと口を開く。
「初めてお目にかかる、子爵殿」
愛想のかけらもない冷ややかな声だ。
「初めて、だよな? それなのに何故お前がここにいる」
怪しいものではない。だがいまここにいる時点で怪しいともいえる。
どう対応すればいいのか考えつつ、ジェルヴェも無愛想に返す。
アルテュールは声だけでなく眼差しも冷え切ったものをジェルヴェに向けた。
「妹のことで話がある」
「妹?」
オウム返しに言い、ジェルヴェは夜会で会ったアデールのことを思い浮かべた。
そしてジェルヴェもまた冷え切った眼差しを向ける。
この男がどこから入ってきたのかなど、すでに頭の隅に追いやられている。
「俺は話などないぞ」
「アデールに近づくな」
ジェルヴェの言葉に即座に切り返す硬質な声。
ジェルヴェは嘲るような笑みを浮かべる。
「近づくな? あの娘は喜んでいたぞ? 恋路の邪魔はよくないんじゃないのか?」
そう言うジェルヴェの頭の中から、首筋の傷のことはすっかり抜け落ちていた。
都にいたころもたびたびあった修羅場。
妻を、恋人を寝取られた男たちが、さもジェルヴェだけが悪いかのように怒りをぶつけてきたのを思い出す。
くだらん、とジェルヴェはソファにどっかり腰を下ろした。
アルテュールの表情は変わらない。真意の読み取れない顔。だが、瞳にははっきりと怒りが宿っている。
「ならば、お前はアデールを愛していると?」
その言葉にジェルヴェは声を立てて笑う。
「なんで俺が初対面の女を愛しているんだ。しかもあんな小娘」
アルテュールの神経を逆なでするだろうことはわかっていたが、とくに気にせずに言った。
言った瞬間、なにか痺れるような感覚を首筋に感じ、ジェルヴェは無意識に手で触れる。
そしてこの一見冷静そうな男も怒り狂うだろうかとちらり見上げた。
だがアルテュールは相変わらず冷たい眼差しをしていたが、安堵のようなため息をついた。
「子爵。再度言う、妹には金輪際関わらないでくれ。アデールが君を訪ねようと無視してくれ」
「さぁ約束はできんな。俺は来るものは拒まず主義でね」
実際のところ面倒を抱えてまでアデールに会うつもりもないが、素直に頷くのもつまらない。
「………子爵。アデールは君がこれまで関わった女性の中で一番純粋だ。君が戯れであっても、アデールにとっては本気だ。そしてアデールは真っ直ぐすぎる。この次、君に会おうものなら、アデールはきっと君から離れなくなるぞ」
「心配無用」
「………愚かな人間の男め」
ぼそり、アルテュールが呟いた。
ジェルヴェは聞きとれずに怪訝にする。
瞬間、目が合った。
アルテュールのサファイアのような瞳が、一瞬金色に光る。
不意にジェルヴェの背筋を冷や汗が伝った。
「アデールに近づかぬと、言え」
一層に冷たく、静かであり、だが有無を言わせぬものがあった。
ジェルヴェは全身に圧力のようなものを感じ、それを取り払うように首を振った。
「しつこいな。……たかが領主の娘がどれほどのものだというのだ」
だんだんとジェルヴェは腹がたってきた。
手を出したと言っても、キスをしただけなのだ。
それも一回だけ。しかもそのときに――――。
ふ、とジェルヴェは眉を寄せた。
じくじくと、首筋が熱をおびいているような気がする。
「……田舎者がうるさいんだよ。ったく、言われんでも近づくか。あんな箱入り娘、まったく興味などないッ」
妙な体調の悪さに、ジェルヴェはイライラとして言った。
だが言った瞬間、今度ははっきりとした痛みを感じた。
首筋から胸元へ。突き抜けるような、痛みが走る。
「……っ」
思わずジェルヴェは顔をしかめた。
そしてその様子を見ていたアルテュールもまた顔をしかめる。
「………まさか貴様」
驚愕するようにアルテュールが呟く。
つかつかとジェルヴェのもとへアルテュールが歩み寄る。と、ジェルヴェを押し倒した。
突然のことに唖然としてジェルヴェはアルテュールを見つめる。
体格の差はあまりない。力だけならジェルヴェのほうが強そうにも見えるというのに、あっさりと組み敷かれた状態がジェルヴェには認識できなかった。
アルテュールの手が伸び、ジェルヴェの襟元に触れる。そして破るように胸元を開いた。
鍛えられた胸元がわずかに空気にさらされる。
ようやくジェルヴェは我に返り、ぎょっとして抵抗した。
だがアルテュールは馬乗りになり、想像できないほどの強い力でジェルヴェの動きを封じる。
「お……おいッ!! 俺はそっちの趣味はないぞッ!! いくらお前が女装したら綺麗かもしれないだろうがな、俺は女しか―――」
伸びやかなアルテュールの指がジェルヴェの首筋に触れた。
驚きに目を大きく開いたアルテュールの視線と、指先が首筋から胸元へと降りていく。
その指の冷たさと状況に、「おいっ! 離せ! 俺は女が好きなんだー!!」と、ジェルヴェは喚いた。
だがそんな叫びなど聞こえていないかのようにアルテュールはジェルヴェの胸元を見つめ、眉間にしわを寄せた。
厳しい表情をしたアルテュール。
「……"儀式”はまだ途中だったと言っていたのに!」
儀式――?、とジェルヴェが問い返すと同時に、アルテュールはジェルヴェから勢いよく離れた。
「なんなんだ、お前は!?」
悪態をつきながらジェルヴェは身を起こす。見てみればシルクのシャツは無残に引き裂かれていた。
アルテュールはしばし黙して、ジェルヴェに視線を止めた。
「再度忠告しておく。アデールが明日訪れるだろう。だが、なにを言われても拒否するのだ。決してアデールの話を聞いてはならない」
口を開こうとするジェルヴェは、アルテュールの強い眼差しに黙る。
「いいか、拒否のみだ。例えどれだけ苦痛が伴おうが、アデールを受け入れるな。それが―――君のためだ」
なんだ苦痛って、とジェルヴェが問うとした。
『人間の男ジェルヴェよ。お前の、そして一族のことを思うなら、お前にはアデールを拒否する道しかない。
―――忘れるな』
アルテュールは口を動かしていない。
それはまるで直接頭の中に話しかけられたような、そんな感じだった。
呆けるジェルヴェの目の前で、アルテュールがマントをひるがえす。
空気がざわめくように動く。
そして、霧散するように、アルテュールの姿が消えた。
バタン、と大きい音がする。見れば窓が振動に揺れていた。
部屋の中にはジェルヴェしかいない。
先ほどまで目の前にいたアルテュールはいない。
ジェルヴェはこれ以上ないほど大きく口を開けて、立ち尽くす。
「………な……な……なんだ!??」
静かな部屋に、ジェルヴェの呆けた叫びが響いた。
そして、それから数十分後、鏡を見たジェルヴェは再び叫ぶこととなる。
ジェルヴェの首筋から心臓の辺りにかけて、赤黒い血管のようなものが浮き上がっている。
それは心臓のある部分で蜘蛛の巣のような模様を描いていたのだった。
BACK TOP NEXT
2006,10,4
|